ピアノグレード、合格を目指すのもいいけど練習はほどほどに
ヤマハグレード7級Bの変奏例を紹介します。
ヤマハピアノグレードの内容が一部が変更になりました。
詳細は、ヤマハ音楽振興会の公式サイトで確認できます。
私は現役の試験指導者ではありませんが、これまでグレードで学んだ経験をもとに、変奏例やコード進行などを発信しています。
ここで紹介する内容は、「この通りに弾けば合格できる」というものではなく、こんなふうに弾いてみたいな、と感じてもらえるようなアイディアの一つです。
グレードで学べる即興演奏やアレンジの考え方は、音楽を自由にするための素晴らしい仕組みだと感じています。
一番伝えたいのは、テストのための音楽ではなく、課題をきっかけに曲を作ったり、和音をつけたりして楽しむこと。
そんな思いでいるので、今回も課題をもとにした変奏(アレンジ)例を紹介しますね。

ここでは、合格率を上げることよりも、楽しむためのものとして扱っています。なので勉強はほどほどにね。
掛け算の九九と似たシステム
即興の練習では、曲の構成、小節数の配分、超基本のコード、そしてさまざまなキー(調)を学びます。これを身につけておくと、曲のアウトラインが自然と見えてきます。
私は、この勉強が「掛け算の九九」にとても似ていると思っています。
九九は学校の勉強で終わるものではなく、買い物でのちょっとした計算や、生活の中で使える「便利なシステム」
このシステムを応用することで、体感覚的に倍数で増えたり減ったりするのがわかりますね。
掛け算の九九が計算の土台になるように、即興の学びは、曲づくりやアレンジの「土台」です。
7級B/変ロ長調3拍子
課題
 和音をつけてみてください。(試験の時はフォローあり)
和音をつけてみてください。(試験の時はフォローあり)
なんてことのない曲ですか、けっこう手こずると思います。
練習では考え込まずに、これだと思う和音をとにかく弾いてみることです。
コードづけと伴奏形
1 左手をのばす
![]()
2 伴奏形
3 工夫して素敵なコードに
メロディー変奏の例
1 変奏
2 応用編(ステキ)
3 実際に多い演奏例
7級の即興を練習している人だとこんな感じになります。試験でこれを弾いても、もちろん問題ないと思います。
ヤマハグレードは年齢に関係なく受験できます。
とはいえ、もしも小学生でここまでできるのなら、すごいと思いますよ。
とにかくたくさん弾いてみる
みんな、即興演奏を練習の量が足りないなといつも感じています。
「楽しく弾きましょう」というのは本当だけど、その手前ではあまり楽しくなくて、少し根気が必要かもしれません。
たくさん弾いてみて、試してみること。
私がこうしていろんな曲を作る人になってからも、うんと昔にやっていたことを、いまだに考えて、弾いて録音して、楽譜にしてというアウトプットをしているのだから。
とにかく思いついたら、すぐに弾いてみるといいです。
ピアノを弾く環境づくり

環境を整えて真面目に取り組む人は少数派だと思いますが。
すぐに鍵盤を弾ける環境づくりも大切ですね。
特に冬は、寒い部屋にピアノがあって、暖かくなるまで時間がかかったりすると、練習が面倒になります。
なので60鍵盤などの小さなキーボードを用意しておくことがかなりおすすめ。
それで、部屋の寒さや鍵盤の冷たさから解放されるし、すごく良い方法だと思います。
練習回数との関係

10回中、1回上手くいったらその感触を覚えておいて、同じことを別の課題でやってみる。
でもこれがうまくいきそうで、なかなかうまくいかないんですよ。またはじめに戻ってしまうんですね。
それで、苦手意識を持って練習をやめてしまう。
しかし淡々と100回練習すると、不思議とつまづきもなくなって、なんとなく形になっていきます。
しかし練習は量がすべてではありません。その数回の手応えを大切にすること。
それが「ほどほどに」という意味です。
100回を練習して、やっと3、4回奇跡的にうまくいったなと思うような仕上がりも出てきます。
それは変奏力だけじゃなくて、コード付けも同じことで、たくさん弾いていくうちに、次に何のコードが来るのかは理論ではなく、体感的にわかってきます。
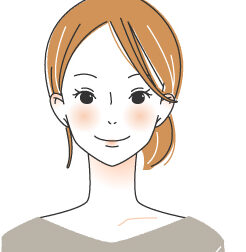
クラシックピアノだけで育ってきた方も、オリジナル作品に挑戦したい方も。
今日の学びが、その一歩になることを願っています。
練習していると、思うようにいかない日もあれば、小さな成功が嬉しくなることもあります。 積み重ねの中で「こういうことだったのか」と腑に落ちる瞬間があるでしょう。 7級の即興や変奏を深めたいときに役立つ記事はこちら。
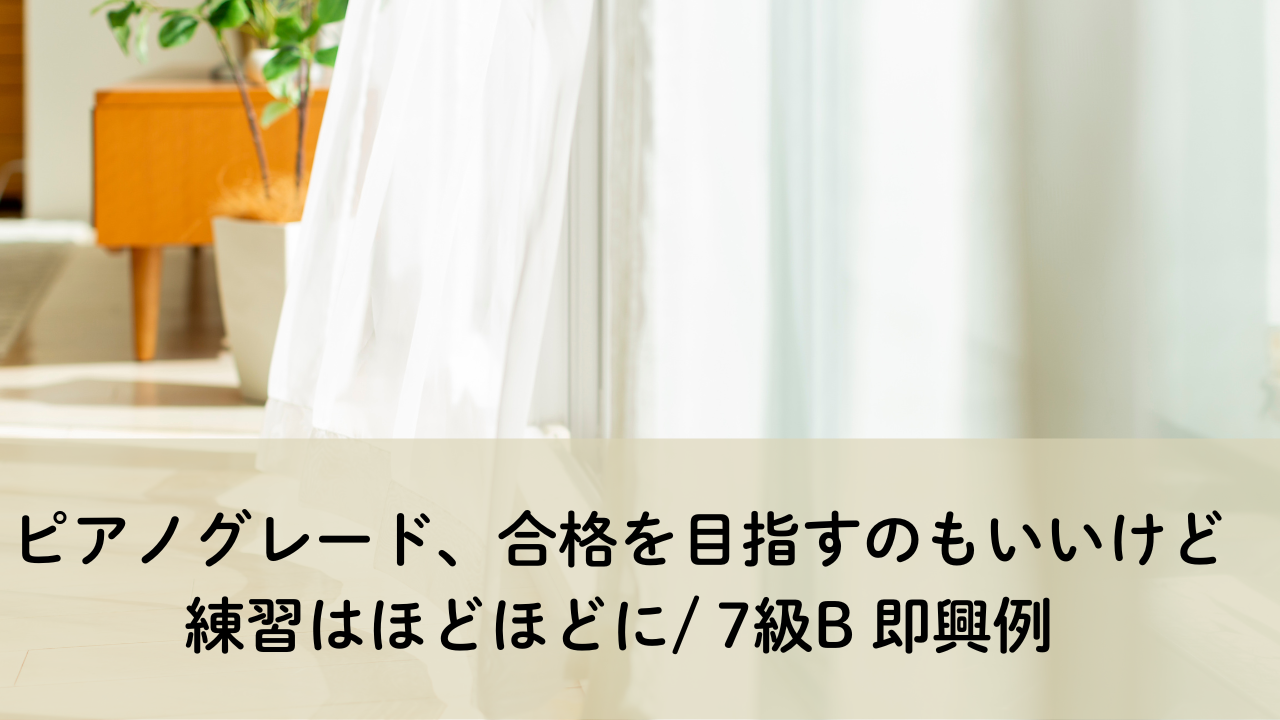
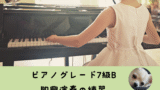
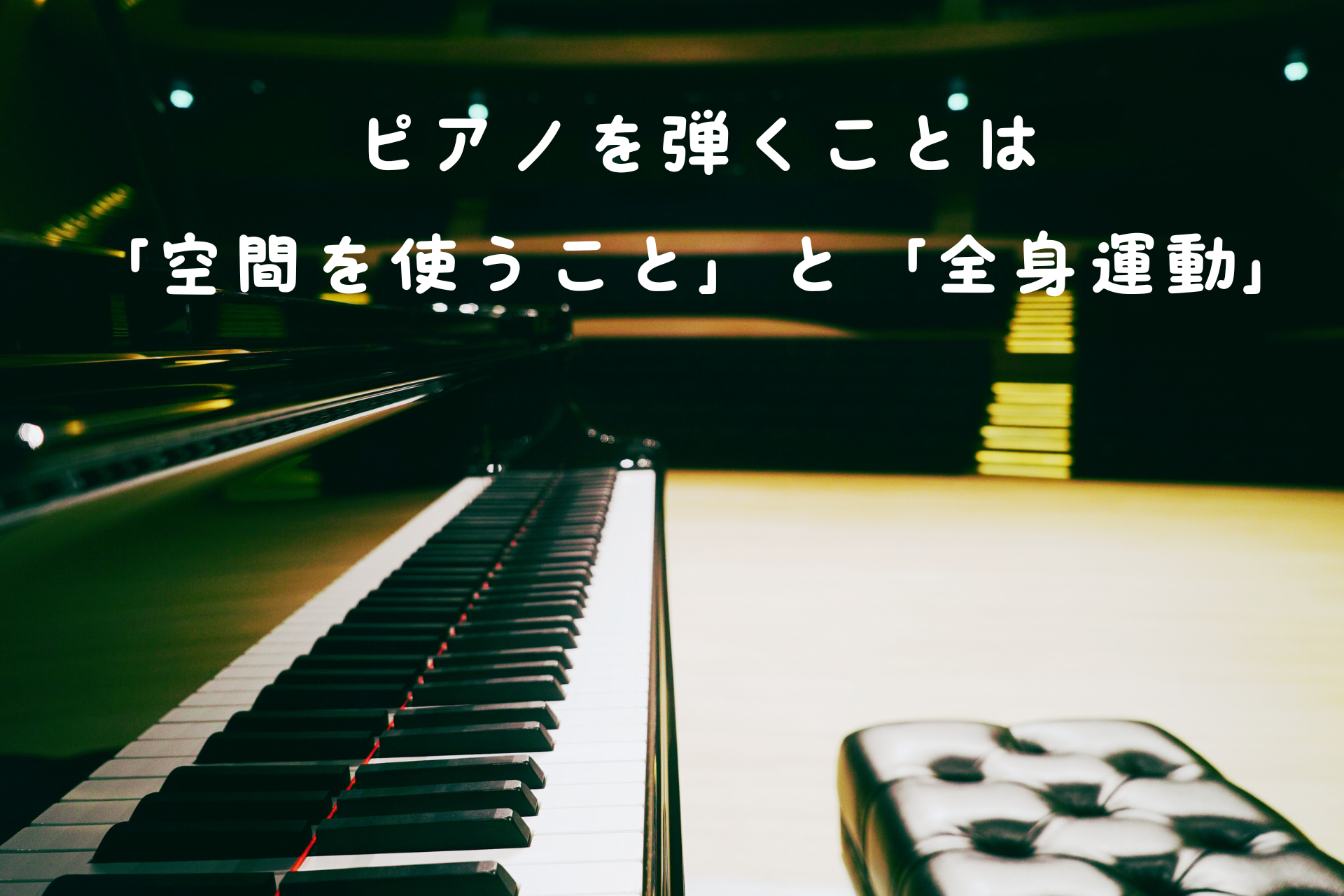
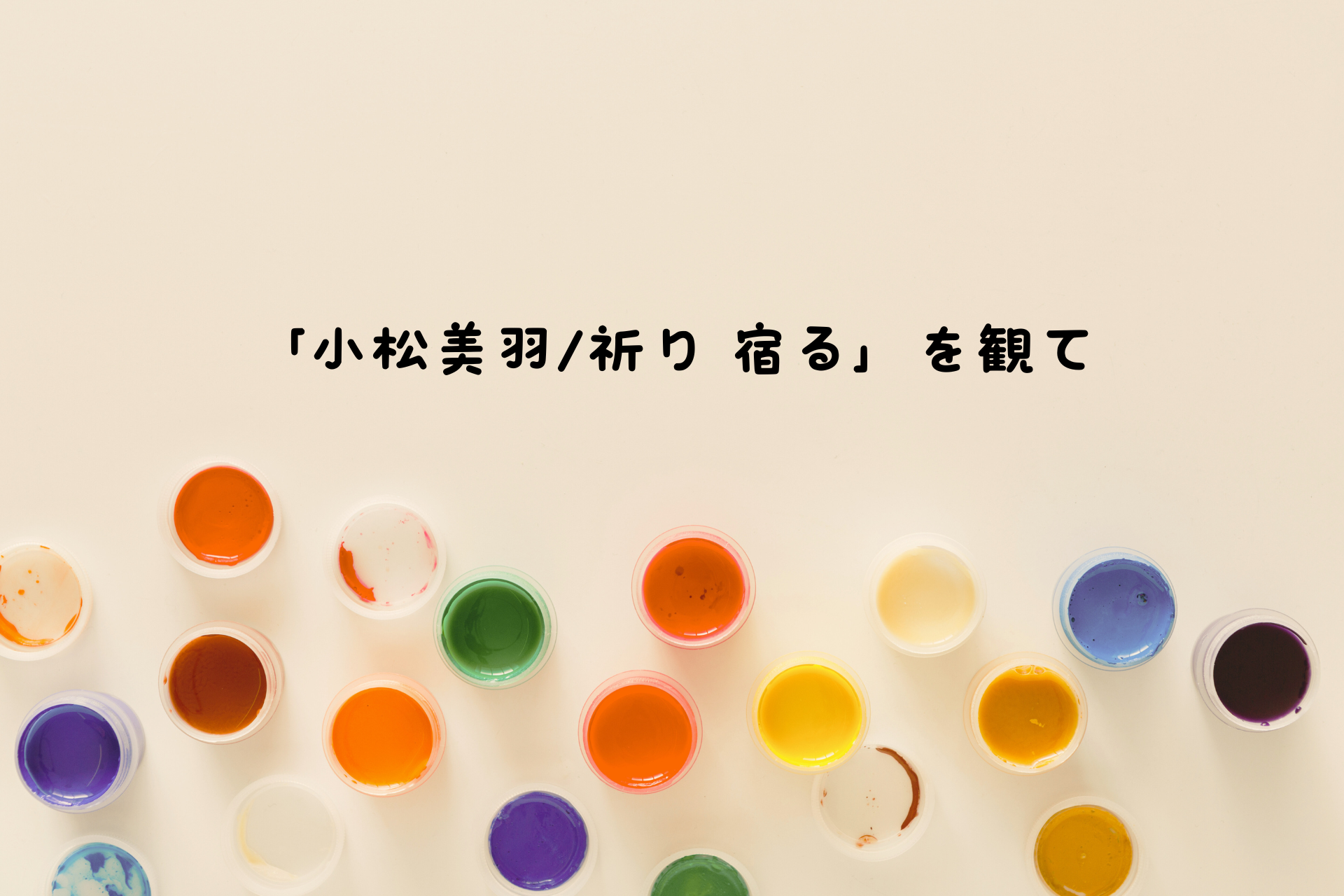
コメント